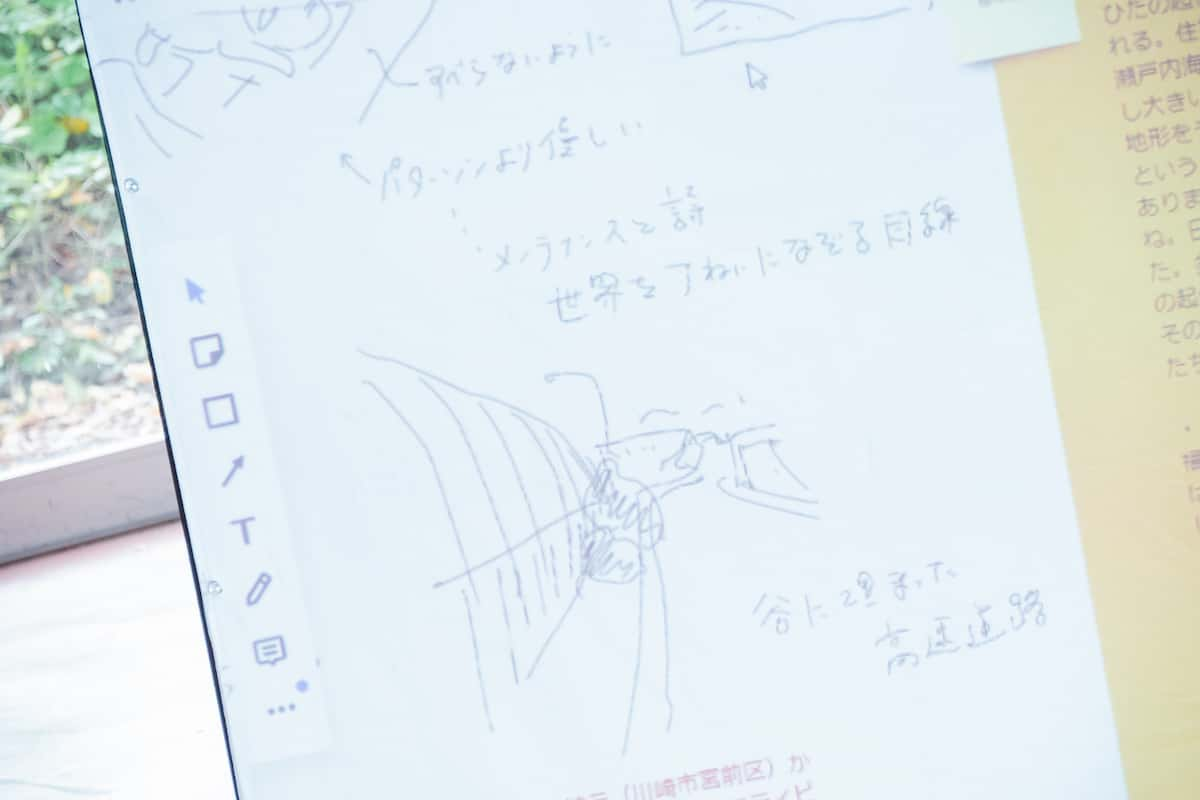平倉圭:
10秒動画をやった後に、みんなで撮りためた動画を素材として共有して、一人ひとりがこの素材全体から映像作品を作ろうということになった。それが最初の「RAUとしてのアウトプット」の試みですね。
藤原徹平:
自分で撮った映像だけまとめる場合と人の映像も一緒にまとめる場合で、感覚がだいぶ違うな……という話になりましたよね。自分で撮ったものはひとつの身体性で撮れてるからわかりやすいんだけど、人のものを混ぜていくと難しい、というような。
「何を撮るか」というテーマを設定していくと、人が撮った映像も素材として選択できるようになるということもわかってきた。そのあたりをもうちょっと深掘りしていくと、みんなで共有できる身体性とは何なのかということが見えてくるのかもしれない。
三宅唱:
途中で〈土木〉を動詞に落とし込んでいく、という試みをやりましたよね。あれはどういうきっかけでしたっけ?
藤原:
受講生のユニ・ホン・シャープさんが「濡らす」という話を出してくれたことでしたね。
三宅:
そうだ。僕が最初、「雨の日はぜひみんな撮ってください」っていうオーダーを出したんですね。というのも、雨は土地の上を流れていくから、雨の行方を辿るようなカットを並べて編集すると、その土地の輪郭のようなものが見えてくるんじゃないかな、と考えてみたんです。すると、ユニさんが「フランスは最近雨が降らないんで、濡らして撮りました」って言って。そのとき「そうか、『濡らす』。それが〈技〉なんだ」っていう発見があった。「雨が降る」という言葉に留まると自然現象をただ眺めている感じでしかないわけだけど、「濡れる」という言葉で表現すると土地の「肌」のディテールが官能的に浮かび上がってくるような感触がある。そこからさらに進んで「濡らす」という自動詞にしたときに、グッと〈技〉が見えてきた……〈技〉って人の能動的なアクションのことか!と。そして、これは「濡らす」以外にもあるんじゃないか!と盛り上がったんですよね。個人的には、この夏は「動詞を探し続けてた」という感じがあります。
藤原:
なるほど、「濡らす」というのが、人間による土地の形質の変更に関わっているってことですね。
三宅:
そうそう。そこからすぐ「掘る」という言葉が出て、穴掘りチーム(*10)が生まれたり。
藤原:
それで言えば「メンテナンス」の話題も出ましたね。最終的には今「ケア」っていう言葉になってるけど、要するに、土地に対する「ケア」っていうことが土地の形質に関わっているという認識。土地が常に不可逆的に変化していることに対してケアをする……維持しようとしたり、あるいはそれを積極的に変えようとしたり、補修したりとか、そういう変更に関わろうとすること自体が土木なんですよね。その前提を共有してないと「濡らすことは土木だ!」って言っても何だかわからないけど、あの「雨が降らないんで濡らしてみました」というユニさんの応答は本当にすばらしくクリエイティブだったと思う。
三宅:
つい先日みんなの作品をまとめて見ましたが、大げさでなく予想以上に興奮しました。RAUが始まったときには未知だった風景、知らなかった体験がここにあるぞ、と。
僕にとっての映画の体験というのは、単純に言うと「映画館に入って映画を見て外に出たら、さっきまでの風景が全然違って見える」かどうかが重要で。映画館に入る前は単なる通行人や風景だったものが「うわっ、あのおばあちゃん、超素敵」「夕方の光がこんなに美しいのか」みたいにリフレッシュされる感覚が訪れるかどうか、それが映画の面白さの僕なりの定義というか、皮膚感覚としてあるんです。最終日に上がってきた作品の大半でそういう経験ができたし、RAUという機会を通して明確に、自分が住んでいる街……街っていう言い方ももはや違う、土地や「大地」みたいなことなのかな、その認識が変わったという気持ちがある。それも、自分ひとりで変わったんじゃなくて、RAUのメンバーたちの作品によって、あるいは、とともに変わるという経験ができたと僕は思っています。
平倉:
今年は全員オンラインで、同じ物理的空間を共有していないという状況の中で、結果的に濃い共同性が生まれたのはすごいですよね。ワークショップの時間の後も「放課後」って言って、毎回のように三宅さんも残ってくれて、23時くらいまでずーっと、みんなで話をしているじゃないですか。
藤原:
けっこう、意識朦朧としてくるときもありますね。
平倉:
自分ひとりの中で追いかけきれないことも、とにかく話して考えるという時間が生まれて。やっぱり直接会えないからなのか、とにかく話すことを求める気持ちもあるし。ただ単に一緒にいて慣れ親しんだ感じが生まれてくるというよりは、何か具体的にアイディアを出したり、撮ったものを互いに見たりっていうことを通じて、考えとか興味、問題意識を媒介として人が時間をかけて繋がっていくということが、直接会ってないことでなんだかすごく、本当に起きたなという感じがします。私も大学でワークショップみたいな授業を今まで何度もやってきているんですけど、二、三日で終わっちゃうことも多くて、楽しいんだけど一過性の風みたいなものになってるような感覚があった。でも、今回は考え方とか、都市の見え方が変わるところまで本当にきてるなと思います。自分の体とか歩き方とか、転び方も、変わってきたと思う。
三宅:
そうですね。たぶんオンラインだろうがオフラインだろうが、大して目的がなければ”繋がり”感以外は特に何も生まれないと思うんですが、RAUには「土木と詩」というテーマがあって、しかもそもそも全員があんまりわかってない、というのがポイントだったんだなと改めて思います。一方的な伝達やレクチャーにはなり得ない。
自分自身も手探りだから、「俺、先週と違うこと言ってるな!」っていうことがたくさんあって。大丈夫かな?と立場上反省したりもしたときもあったけれど、別に誰も問題にしないし、むしろ、前に進んだことになるっていう(笑)。「これがアリな環境ってなかなかないよなあ」と思いましたね。しかも、会ったことない人たちとそういう信頼関係がいつのまにか生まれた。もともとの予定時間と放課後の時間でやり取りを重ねることで、僕もどんどん不安や気負いがなくなって皆さんを信頼して、一貫性はなくても考えついたことはとりあえず試しに言ってみるというモードに切り替えられたのが、本当に幸福なことだったと思います。
藤原:
こういう対話の場って、ありそうでないですよね。大学は評価を基準にした言葉を選んでしまうし、普通にプロジェクトで何かを作るときには締め切りがあったりするし、プロジェクトも実は最後に何を作るかが決まっていることが多いので、どうしても予定調和的な対話になっちゃう。だけど、RAUは本当に自由に話せて、しかもそれに対して創造的な応答が出てきて、素晴らしいなと思っています。これからこのプログラムを冊子にしたり、シンポジウムをしたりと「まとめ」に入るんだけど、この素晴らしさをまとめるためにどうすればいいのか、まとめる過程で何を選んで何を切り捨てればいいのか。いやー、ちょっと僕にはまだ全然わからないな……。
世界はなぜ〈詩〉を必要とするのか

平倉:
RAUのホームページには「YARD(ヤード)」という名前をつけましたが、これも途中で出てきた言葉で。横浜の沿岸は一帯が埋め立てられていて、コンテナとか資材とか、とんでもなくスケールが大きいモノの置き場所になっている。ああいう場所はすごく面白いよねという話になって。その資材置き場とか、作業場という意味の「ヤード」が途中からキーワードになっていったんですよね。で、ホームページを作ろうという話になったときに、RAUで作ってる素材をとにかくドンと置く場所というイメージがしっくりきたので、「ヤード」と名づけた。ウェブなので外部に対して開けてはいるんだけど、「これはこういうものです」ってプレゼンするような感じでも、少なくとも今はないのかなと。ここで生まれている素材を、何になるのかはまだわからないままにゴロゴロ置いてる感じですね。
三宅:
ものごとを伝えるには「物語」という形がまずありますよね。でも今回は「土木と物語」ではなく「土木と詩」であることがやっぱり参考になるのかなと思っています。途中で松尾芭蕉の話がありましたよね?
平倉:
はい。
三宅:
五七五の本文は知っていましたが、実はその前に前文があるんだっていうことを僕はRAUではじめて知って、参加者の作品も「前文プラス本文」が一つの型になっていきましたが、プロジェクト全体としてもその「前文プラス本文」の呼応関係みたいなものがうまく作れれば、伝わる回路になるのではないかな、と。詩という言葉は、人によって定義やイメージがあまりにまちまちなので安易には使えないというのも、今回の面白さでしたが。
平倉:
そうですよね。〈土木〉の定義があった次の回で、「じゃあ、平倉さん〈詩〉を定義して」って言われて。「いや無理だし、無茶だな〜」と思いつつも(笑)、この場所でやるなら、「詩」を言葉の表現に限定しない形で定義しなきゃなと思ったんです。
そこで仮に私が出した拡張的定義が、「詩は、ゼロ人称の心物の傾きを制作する文である」というものでした。ポイントはまず「文である」というところ。5世紀末頃に、中国南朝梁の劉勰という人が書いた『文心雕龍』っていう文学理論書があるんですが、その中で、〈文〉というのはこの地球上にあるパターンすべてのこと、山脈も川の流れも虎の模様も雲の色どりも、全部〈文〉なんだということが書かれている。そのありとあらゆる〈文〉の中に、人間の言葉もあるわけです。この観点だと、土木も〈文〉だということになる。
第二のポイントは「心物の傾き」で、これは思いや志といった「心の傾き」と、土地の傾斜といった「物の傾き」を区別せずに扱ってしまう。さっきの映像の話で私が崖の上で「おお」って思うとき、心も傾いているけど、体も傾いてて、それを支える周囲の環境も傾いているわけですよね。心はそもそも体の中だけにはなく、体の外の物質的環境に広がっているし、環境によって作られてもいる。その「心/物」にまたがる「傾き」の操作を、もう〈詩〉と呼んでしまおうと。これによって土木じたいを詩と呼ぶことが可能になる。
最後のポイント、「ゼロ人称」というのは日本文学者の藤井貞和の言葉を借りたんですけど、詩じたいから生み出される表現主体のことです。そこに、私としては「私の消滅」という意味も込めたい。例えば、松尾芭蕉の「五月雨をあつめて早し最上川」っていう句、あれは先に地形の記述から始まるんですよね(*11)。山形の山間を水が流れていて、崖地にある滝やお堂が垣間見えて、最後にぐっと「水みなぎつて船あやうし」、と。そう述べてから、「五月雨をあつめて早し最上川」の句がくる。地形の描写から、地形を集めるように流れてきた雨で水勢が強くなり、水面が大きく盛り上がって、舟に乗ってる自分が傾く。危うい。そこでふっと、描写している芭蕉という「私」が消えて、「五月雨をあつめて早し最上川」という、世界全体の傾きを表した文になる。その世界には、自分と環境、心と物の傾きが両方含まれていて、だけど私視点じゃないっていう。句自体が生み出すこの、自分と環境、心と物をともに含んだ世界の眺めをゼロ人称と呼び、その傾きを作るのが詩だと定義してみた。土木もそのように、世界に心物の傾きを作るんじゃないか。――そういう様々な傾きの断片をとりあえず集めていく場所として、「ヤード」があると考えています。

藤原:
僕としては、ただそこにマテリアルを提示する場であるということで、参加した人たちがこれから何かをやっていくときに「ヤード」が助けになるといいなというのがありました。
あともうひとつ重要なのは、例えば、フルクサス(*12)でもブラック・マウンテン・カレッジ(*13)でも何でもいいんですけど、芸術に大きな役割を果たした共同体とか集合体って、結局、何やってたんだかよくわからないんですよね。
平倉:
うん(笑)。
藤原:
だけどやっぱり「仲間だったんだな」っていう感じの、それぞれに通底する大きな世界観みたいなものを伴った芸術運動だなとは思う。我々もそういうところを目指してるんだと思うんですけど、今年の制作物が多少ちんぷんかんぷんなものであっても、ここに参加した人たちが作る、三宅さんがRAUに参加したから生まれてくる視点がそこにあるかもしれないし、平倉さんが作る次の言葉とか僕が作る次の建築とか、そういうものを後から見たときに「一番重要だったのはRAUなんじゃないか」みたいなことを、後世の、我々が作った制作物を分析する人が考えるためのマテリアルになっていればいい。「藤原が言ってること、ほとんどRAUの内容じゃないか」みたいな批評が出てきたら最高だなと思うんですよね。そうなりかねないくらいのインパクトを、僕にとってはRAUは持ってる。
三宅:
「三宅の映画には土木が映ってる」って言われてみたい!
藤原・平倉・三宅
(笑)。
藤原:
ひとりの中心的な思想家が何か言葉を書いて、それに沿って制作するという集団じゃなくて、みんなで「この世界とは何なのか」っていうことを一緒に考えているところに、このRAUの特徴がある。
松尾芭蕉が面白いんじゃないかと思ってると平倉さんに、ずっと言ってたのも、ほぼ勘で、しかし、平倉さんはそれを深堀して、すごい鉱脈を見つけてきてくれた。あの流れは本当に痺れました。
中谷宇吉郎(*14)が「科学とは何か」ってことを書いた短い文章で、科学とはあくまで人間の眼を通じた世界の姿で、本当は世界は科学が定義するようにはなってないかもしれないし、おそらくなっていないだろう……と明言しているんですよね。物理学が定義するすべての法則というのは「人間の眼にそう捉えられる」っていうこと。つまり〈文〉ですよね。科学とは〈文〉だって、中谷さんはほぼ定義している。それが科学の本質であり、限界であるっていう。だから世界を世界のままに語るのが科学だと思ったら大間違いだということを、『科学の方法』(岩波書店, 1958)という本で書いている。科学者はそこから理解しなければ始まらない、と。僕は東洋的な〈文〉の考え方に中谷さんの考えも含まれているように感じます。だとすると、この「ゼロ人称の心身の傾きを制作する文」っていうのは、科学の前提にもつながるすごく重要な定義かもしれない。
次なる思考、次なる制作へ

藤原:
このプログラムは「都市と芸術の応答体2020」と銘打っているので、2020年度の事業というまとまりは一応ある。でも、受講生が「これから何をやっていきたい」という企画書を全員出してくれていたり、僕自身もRAUを通じて「次なる建築」「新しい土木」というようなことが見えてきた。これらの活動は単に2020年に収まるものではないと思っています。
特に、この間の講義で受講生の持田敦子さんが「土木は生活を仮定する」という定義を作品説明のなかで使っていたんですが、それを聞いて、仮定するものの将来の時間軸を考えることで土木の規模は変わるんだなとも思った。今日そこに座るだけでいいんだったら、ちょっと草を刈ってレジャーシートを敷く程度の形質の変更でいいけど、千年先まで保とうとすると大きなコンクリート壁だったり、塀を作らないと……となるわけで、生活を仮定したときの時間の長さみたいなことの議論が、都市政策では本来なされなくてはならない。それがない中で普段のあらゆる会話ができてしまっているのは、すごく問題だと思うんです。普通に「言葉が通じている」のに、それぞれの仮定が違うために「話が通じていない」というか。「千年という時間の単位に対して、なぜ今対応しなければいけないのか」という話を誰もしない。
なので、RAUの2020年がなにか解を提示し得たかどうかはわからないけど、少なくとも言えるのは、この2020年でひとつ区切りがつくとは到底思えないので、今年の議論を2021年、2022年と継続していかないといけないということですね。そうなると、三宅さんは来年忙しいんでしょうけど、三宅さんとも今年で終わりってことにはならないんじゃないかなと思う。
三宅:
お、おお?
藤原・平倉・三宅
(笑)。
三宅:
でも、そうしたいですね。今年の変化ぶりを思うと「置いてかないで!」って感じ。「今どうなってるか、ちょっと教えてよ」みたいに追っかけ続けたいです。
藤原:
今の自分は、来年違う人と、全然違うRAUをやるとか、ちょっと想像できない感じにはなってます(笑)。
三宅:
僕個人としては、2020年にこれがスタートしたというのも大きかったのかもしれません。自分の中にこの10年くらいあった生きてることのモヤモヤみたいなものが、RAUによって少し解決したような気がするんです。
そのモヤモヤは、大きくふたつあって。ひとつは、昨日あったことすらもう誰も覚えていないような時間の早さというか「現在しかない」という感覚。もうひとつは、この世にはすでにあまりにも映像がたくさんあって、その価値もどんどん暴落しているということ。それが重なって、「今、ここ」がどうでもいいものになっちゃってモヤモヤする、というかんじです。そこで、RAUの議論の途中で、藤原さんがコンポジションに対する批判についてお話されたことがありましたよね?「切り取った『今』だけで物事を扱うことにはもはや何の意味もないんじゃないか」とはっきり口にすることで、突破口が見えた。
そういうことを踏まえて今回の「土木と詩」について考えたときに、さっき言った「この外にもあるんだ」っていう空間的な広がりと、形質のディテールの広がりと、あと時間の前後の広がり……「形質の変更」という言葉が定義にありましたけど、変更するってことは前と後があるってことだから。つまり、「今」目の前にみえている物事を支える空間的・時間的広がりをどう捉えるかということが、モヤモヤから自分を救える方法かもしれない、と。
例えば今朝、横国のキャンパスを一緒に歩かせてもらっただけでも、以前ならきっと「ああ、緑がいっぱいできれいだな」と思うだけだったのが、藤原さんのガイドによって、ここがもともとゴルフ場の敷地で、時代とともにあれができてこれができて、今後はきっとこうなって……という広がりのなかで見られるようになり、するともう全然見えている世界が変わるし、土地の広がりと時間の広がりで自分の体も変わるというか、位置付けが変わる。きっとこれはキャンパス内の話に留まらず、もっと大きな、例えば神奈川県単位で「海と山との間に〈今、ここ〉がある」という感覚にも繋がっていくんだと思います。そういう経験を通して、不思議とRAU以前のモヤモヤが解消されたというか、「今後はそのようにしてものを見ていきたい」っていう感覚が明確に生まれたんです。なので、RAUはこれからも、それをより広げてみていく、よりディテールをみていくようにして進んでいくんだろうなと、僕自身は勝手に期待してます。

この日は座談会の前に、藤原徹平が横浜国立大学の沿革やキャンパスの成り立ちを説明しながら学内を歩く見学ツアーが行われた。
藤原:
平倉さんは?
平倉:
今の話がいい感じだったので、私は別にいいかな……。
三宅:
ちょっと(笑)。
平倉:
キャンパスの話も入ったし(笑)。いや、本当にね、私もRAUが始まってからすごく歩くようになったんですよね。近所の地形を縦断して、無意味に登り降りしたり。
藤原:
修験道ですね。
平倉:
そうそう。でも、登り降りすると土地の形が体に入ってきて「ここは見通しの効かない崖地の細い階段だけど、大きい起伏のこの辺にきっといるんだな」とか「この山の向こうにも、もうひとつ谷と山があって、その後ろに海があるんだな」みたいに、見えていなくても「ある」っていうことがわかる。そう感じるのが楽しくなるし、大事なのはそういうことなんだなと思いましたね。
藤原:
明確な中心もなく全体的に手探りだったからこそ、本当に「学びたい」「考えたい」「このモヤモヤについて更に深く掘り下げたい」という人がたくさん集まって、それをやれる場所になったなという印象があります。自分が素直に感じてる疑問とか悩みも正直にオープンにして、そこからみんな手探りで映像を撮ったり、考えたり、言葉にしたりしていて。漠然とした言い方ですが「いい感じ」だなと。でも、この「いい感じ」が作れたのはRAUの財産ですよね。
三宅:
そうですね。日本だけじゃなくフランスやらベルリンやら香港やらにいる、きっと出会わなかった人が同じ問題についてめちゃくちゃ真剣に考え続けてくれるっていう安心感がすごくあった。
藤原:
そう、安心感がありますよね。信頼と安心感が。
三宅:
そうそう。モヤモヤの内容は個々で違うとは思うけれど、何らかの「わからなさ」を抱えている方たち同士で、自分の体と、プラス、他の人の体を使って一緒に考えるっていう感じがありましたね。
藤原:
うん。みんなの思考はこれからも深まっていくと思いますよ。この間の受講生の板谷幸歩さんの映像もショッキングだったし。
三宅:
あれ、ショックだったなー。悔しくてしょうがない。
藤原・平倉・三宅
(笑)。
三宅:
ロングショットとクロースアップショットをいかに組み合わせるかこそが勝負だろうと、さっき話したように僕は一度すっかり結論づけかけていたのだけれど、おもいっきり覆されましたからね! その手があったか、すごい、と。ロケ地の選択ぶりといい、撮影・編集の選択ぶりといい、強烈な刺激を受けました。
藤原:
考えるだけじゃなくて全員で感じて、それを形に定着させようとする。本当にいい共同体になっているなあという感じがあるので、楽しいですよ。集団としての体として、いつまでも生き続けてほしいなと思います。
1 2 3